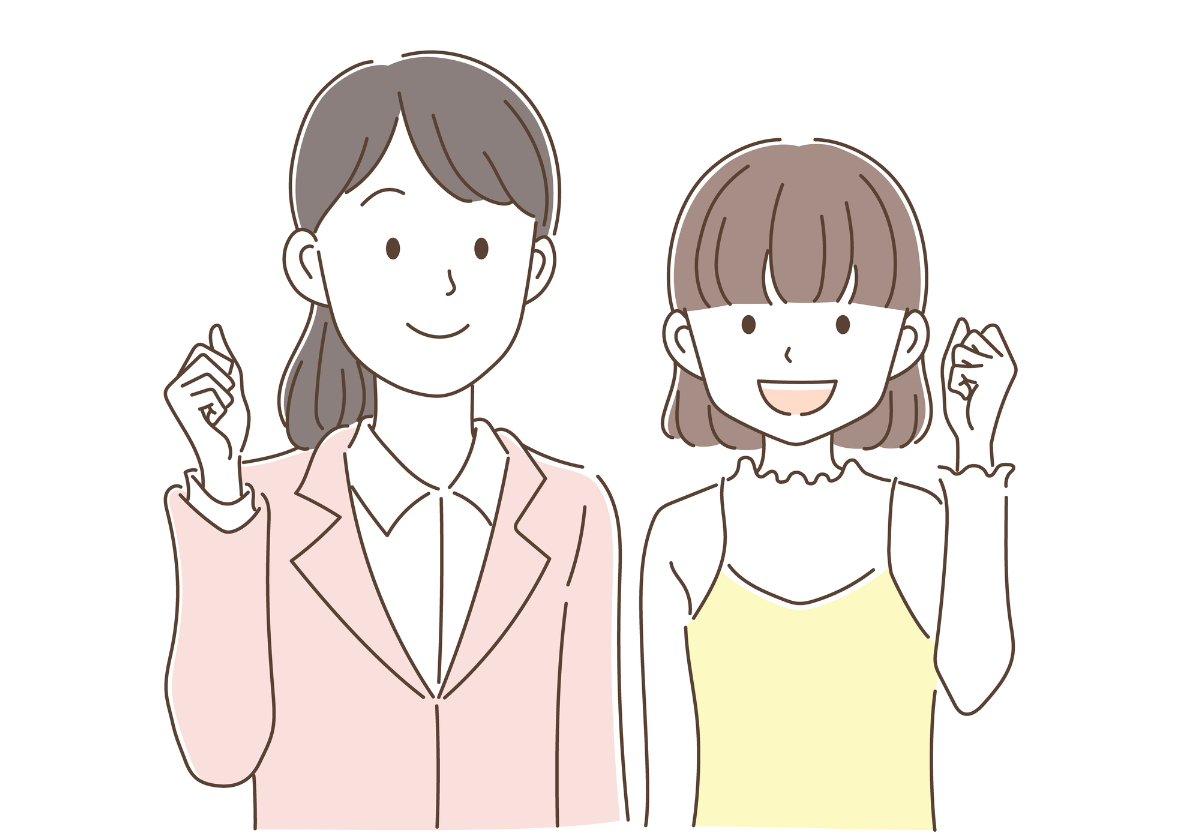共通テスト古文の基本的な特徴と出題傾向
共通テスト古文は、センター試験から形式が変わり、より実践的な読解力が求められるようになりました。お子様の受験対策として、まずは出題傾向を正しく理解することが重要です。古文が苦手なお子様も多いですが、適切な学習方法と教材選びで確実に得点アップが期待できる科目でもあります。
共通テスト古文の出題形式と配点
共通テスト古文の出題形式は、大きく分けて2つの文章読解問題で構成されています。第3問と第4問がそれぞれ古文の問題となり、合計で50点の配点となっています。
第3問では主に平安時代から鎌倉時代の作品が出題される傾向があり、物語や日記文学からの出題が多くなっています。設問数は6問程度で、内容理解や文法事項、語彙の知識を総合的に問う問題が中心です。
第4問では鎌倉時代以降の作品が多く、説話や軍記物語などが題材となることが一般的です。こちらも6問程度の設問があり、文章の流れや登場人物の心情を読み取る問題が出題されます。
両問題とも、従来のセンター試験と比較して文章量が増加し、より深い読解力が求められるようになりました。単純な暗記だけでは対応が困難で、文脈を理解する力が重要になっています。
近年の出題傾向分析
近年の共通テスト古文では、いくつかの特徴的な変化が見られます。まず、現代語訳問題の形式変更が挙げられます。従来の選択肢から適切な現代語訳を選ぶ形式に加えて、文脈に応じた適切な解釈を求める問題が増加しています。
また、文学史的知識を直接問う問題は減少傾向にあり、代わりに作品の背景や時代性を理解しているかを間接的に問う問題が多くなっています。これは単純な暗記学習から、より深い理解を重視する出題方針の現れといえます。
語彙問題についても変化が見られ、古語辞典で調べればわかるような基本的な語彙よりも、文脈から意味を推測する力を問う問題が増えています。このため、多くの古語を暗記するよりも、代表的な古語の意味変化や用法を深く理解することが重要になっています。
文法問題では、助動詞や敬語の知識を問う問題が安定して出題されていますが、単独で文法事項を問うのではなく、文章読解の中で文法知識を活用する形式が主流となっています。
難易度の変化と対策のポイント
共通テスト古文の難易度は、センター試験と比較してやや上昇していると考えられます。特に文章量の増加により、限られた時間内で正確に読解する力がより重要になっています。
対策のポイントとして、まず基本的な文法事項の確実な習得が挙げられます。助動詞の意味・用法、敬語の種類と使い分け、助詞の用法などは、文章読解の基盤となる知識です。
次に頻出古語の語彙力強化が必要です。ただし、機械的な暗記ではなく、語の成り立ちや意味の変遷を理解しながら覚えることが効果的です。現代語との関連性を意識した学習方法が推奨されます。
最も重要なのは読解演習の充実です。様々な時代・ジャンルの古文を数多く読み、文章の展開パターンや表現技法に慣れることが高得点への近道となります。
効果的な古文学習の基礎固め
古文学習において最も重要なのは、確実な基礎力の構築です。多くの受験生が古文を苦手とする理由は、基礎的な文法や語彙の理解が不十分なまま応用問題に取り組んでしまうことにあります。お子様には段階的で体系的な学習アプローチをおすすめします。
古典文法の習得方法
古典文法は古文読解の根幹となる重要な要素です。まず動詞の活用から始めることをおすすめします。四段活用、上一段活用、上二段活用、下一段活用、下二段活用、カ行変格活用、サ行変格活用、ナ行変格活用、ラ行変格活用の9つの活用パターンを確実に覚える必要があります。
活用の学習では、単純な暗記ではなく音読を重視した方法が効果的です。「咲く、咲かず、咲きて、咲く時、咲けば、咲け」のように、実際に声に出して覚えることで、リズムとして身体に染み込ませることができます。
助動詞の学習では、意味・活用・接続の3要素を関連付けて覚えることが重要です。「る・らる」「す・さす・しむ」「き・けり」「つ・ぬ」「たり・り」などの主要な助動詞について、例文とともに確実に習得する必要があります。
敬語の理解も古文読解には欠かせません。尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別と、それぞれの代表的な語彙を覚えることで、登場人物の身分関係や場面設定を正確に把握できるようになります。
古語の語彙力強化
古語の語彙力は読解速度と正確性に直結する重要な要素です。効果的な学習方法として、語源や語の成り立ちを意識した覚え方が推奨されます。
例えば「あはれ」という語は、現代語の「哀れ」とは異なり、「感動詞的な驚きや感嘆」を表す語であることを理解する必要があります。このような語義の変遷を知ることで、より深い理解が可能になります。
多義語の学習では、文脈によって意味が変わる語に特に注意が必要です。「心」「色」「風」「花」などの語は、場面や時代によって様々な意味を持つため、具体的な用例とともに覚えることが重要です。
季節語や時間表現も古文特有の重要な語彙です。「卯の花の咲く頃」「時鳥の鳴く季節」などの表現から具体的な季節を読み取る力は、作品の背景理解に不可欠です。
語彙学習では語彙帳の活用が効果的ですが、単語を孤立して覚えるのではなく、短い例文や慣用表現とセットで覚えることをおすすめします。
古文常識と文学史の基礎知識
古文常識は、古典作品の背景を理解するために必要な知識です。平安時代の宮廷生活、建物の構造、年中行事、服装、食事などの基本的な知識があることで、作品の理解が格段に深まります。
宮廷の階級制度について理解することは特に重要です。天皇、皇族、摂関家、官人などの身分関係を知ることで、登場人物同士の関係性や会話の敬語レベルを正確に把握できます。
年中行事や季節の行事も重要な知識です。正月、雛祭り、端午の節句、七夕、重陽の節句などの五節句や、花見、月見、紅葉狩りなどの季節の行事について基本的な知識を持つことが推奨されます。
文学史の基礎知識では、主要な作品とその作者、成立年代の大まかな流れを把握することが重要です。『源氏物語』『枕草子』『土佐日記』『竹取物語』『伊勢物語』などの代表作については、あらすじと特徴を理解しておく必要があります。
ただし、詳細な年代暗記よりも、作品の特色や文学的意義を理解することに重点を置くことが、共通テスト古文の対策としては効果的です。
読解力向上のための実践的学習法
古文の読解力向上には、基礎知識の習得だけでなく、実際の文章を使った継続的な練習が不可欠です。お子様の学習段階に応じて、段階的に難易度を上げながら取り組むことが重要です。効果的な読解練習の方法をご紹介します。
音読による読解力強化
音読は古文読解力向上に最も効果的な学習方法の一つです。古文は本来「声に出して読まれる」ことを前提として書かれた文章であり、音読することで文章のリズムや流れを自然に体得できます。
まず正しい読み方を確認することから始めます。歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直して読む練習を行い、助詞や助動詞の読み方に特に注意を払います。「てふ」を「ちょう」、「けふ」を「きょう」と読むような基本的な変換ルールを身につけることが重要です。
意味を理解しながらの音読が次の段階です。単語の意味や文法事項を確認した後、内容を理解した状態で音読を行います。この際、感情を込めて読むことで、登場人物の心情や場面の雰囲気をより深く理解できるようになります。
繰り返し音読により、古文特有の文体に慣れることができます。同じ文章を10回以上音読することで、助詞や助動詞の使い方、敬語表現、語順などが自然に身につきます。
音読練習では録音して聞き返す方法も効果的です。自分の読み方を客観的に確認でき、読みの間違いや不自然な箇所を発見できます。
精読と速読のバランス
共通テスト古文では、限られた時間内で正確に読解する力が求められるため、精読と速読の両方の技術を身につける必要があります。
精読練習では、短い文章を時間をかけて丁寧に読み解きます。文法事項を一つずつ確認し、古語の意味を調べながら、正確な現代語訳を作成します。この段階では辞書を積極的に活用し、語の意味や用法を詳しく調べることが重要です。
精読では文章構造の分析も行います。主語と述語の関係、修飾と被修飾の関係、敬語の方向性などを図式化して整理することで、複雑な文章でも正確に理解できるようになります。
速読練習では、時間を制限して全体の内容把握に重点を置きます。細かい語句の意味にこだわらず、文脈から意味を推測する力を養います。最初は辞書を使わずに読み、大まかな内容を把握した後で、重要な箇所のみ詳しく確認する方法が効果的です。
速読ではキーワードの発見が重要です。登場人物名、季節や時間を表す語、感情を表す語などを素早く見つけることで、文章の概要を効率的に把握できます。
文脈読解のテクニック
文脈読解は古文読解において最も重要な技術の一つです。単語の意味を知らなくても、前後の文脈から内容を推測する力を身につけることで、共通テスト古文での得点向上が期待できます。
接続表現に注目することが基本的なテクニックです。「然れども(しかれども)」「さて」「かくて」「されば」などの接続語により、文章の展開を予測できます。逆接、順接、転換などの関係を素早く把握することが重要です。
敬語の方向性から登場人物の関係を読み取ることも重要な技術です。誰が誰に対して敬語を使っているかを分析することで、身分関係や場面設定を理解できます。
季節語や時間表現からの情報収集も効果的です。「桜の散り始める頃」「月の美しい夜」などの表現から、具体的な季節や時間帯を推測し、場面の雰囲気を想像することができます。
心情表現の読み取りでは、直接的な感情表現だけでなく、行動や会話から間接的に表現される心情を理解する力が必要です。「涙を拭う」「ため息をつく」「空を見上げる」などの行動から、登場人物の心境を推測します。
文脈読解では全体と部分の関係を常に意識することが重要です。細部にとらわれすぎず、文章全体の流れの中で各部分の役割を考える習慣を身につけることが、読解力向上の鍵となります。
おすすめ教材と参考書の選び方
お子様の学習レベルや志望校に応じて、適切な教材を選択することが効率的な学習には不可欠です。古文の教材は多数出版されていますが、共通テスト古文対策に特化した教材選びのポイントをご紹介します。
基礎固め用教材の特徴
基礎固め段階では、文法と語彙の確実な習得を目的とした教材を選択することが重要です。初学者向けの教材では、図表やイラストを豊富に使用したものが理解しやすく、継続学習にも効果的です。
文法書では、活用表が見やすく整理され、例文が豊富に掲載されているものを選びます。助動詞については、意味・活用・接続を一覧表で確認できる教材が便利です。「望月光の古典文法講義の実況中継」や「富井の古典文法をはじめからていねいに」などが代表的な基礎教材として多くの受験生に利用されています。
語彙集については、語源や語の成り立ちについての説明があるものを選択します。単純な羅列ではなく、関連語をグループ化して覚えられる構成の教材が効果的です。「読んで見て覚える重要古文単語315」「古文単語ゴロゴ」などが人気の高い教材です。
古文常識については、ビジュアル資料が充実した教材を選ぶことをおすすめします。平安時代の宮廷生活や建物の構造、服装などを図解で理解できる教材が、暗記に頼らない理解型学習を可能にします。
問題集・過去問集の活用法
問題演習段階では、段階的に難易度を上げながら様々な形式の問題に取り組むことが重要です。まず教科書レベルの問題集から始めて、基礎的な読解力を確認します。
「古文上達 基礎編 読解と演習23」は、基礎から標準レベルの問題が段階的に配列されており、解説も詳しいため、自学自習に適した教材です。各問題に文法事項や語彙の確認ポイントが明記されているため、復習にも活用できます。
共通テスト対策に特化した問題集では、「共通テスト古文のポイント」「共通テスト古文対策」などが効果的です。これらの教材では、実際の共通テストの形式に慣れることができ、時間配分の練習も可能です。
過去問演習は受験直前期に集中的に行います。「共通テスト過去問レビュー」「共通テスト実戦問題集」などを使用し、本番と同じ時間制限で演習を行います。過去問演習では、間違えた問題の詳細な分析が重要で、なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのかを明確にすることが必要です。
塾・予備校教材との使い分け
塾や予備校で使用する教材と、市販の参考書の使い分けも重要なポイントです。塾教材は体系的で段階的な学習が可能ですが、市販教材は特定の弱点補強や追加演習に適しています。
大手予備校の河合塾、駿台、代々木ゼミナールなどでは、それぞれ独自の古文教材を使用しています。これらの教材は長年の指導ノウハウが蓄積されており、効率的な学習が可能です。
個別指導塾や家庭教師では、お子様の理解度に応じてカスタマイズされた教材選択が可能です。特に古文が苦手なお子様には、基礎からじっくりと取り組める個別対応が効果的です。
市販教材の利点は、自分のペースで学習できることと、コストパフォーマンスの良さです。また、複数の著者による異なるアプローチの教材を比較検討できるため、お子様に最適な学習方法を見つけやすいという特徴があります。
教材選択では、お子様の学習スタイルを考慮することが重要です。視覚的な学習を好む場合は図表が豊富な教材を、論理的思考を好む場合は体系的に整理された教材を選択することをおすすめします。
効果的な学習スケジュールと計画立て
共通テスト古文で確実に得点するためには、計画的で継続的な学習が不可欠です。お子様の現在の学力レベルと受験までの残り時間を考慮して、最適な学習スケジュールを立てることが重要です。
学年別学習プラン
高校1年生の段階では、古文の基礎固めに重点を置いた学習計画をおすすめします。週に3〜4回、1回あたり30分程度の学習時間を確保し、文法事項の習得と基本的な語彙の暗記を中心に進めます。
1年生の前期では動詞の活用を完全にマスターすることを目標とします。四段活用から始めて、段階的に全ての活用パターンを覚えます。毎日10分程度の音読練習を組み合わせることで、活用を自然に身につけることができます。
1年生の後期では助動詞の学習に移ります。「る・らる」「き・けり」「つ・ぬ」などの基本的な助動詞から始めて、意味・活用・接続の3要素を関連付けて覚えます。
高校2年生では、基礎力の完成と応用力の養成を並行して進めます。週に4〜5回、1回あたり45分程度の学習時間を確保し、文章読解の練習を本格的に開始します。
2年生の前期では短い古文の精読を中心に行います。教科書の作品や入門レベルの問題集を使用して、一文一文を丁寧に読み解く練習を積みます。現代語訳の作成と、文法事項の確認を必ず行います。
2年生の後期では読解スピードの向上を目指します。制限時間を設けた読解練習を導入し、効率的に内容を把握する技術を身につけます。
高校3年生では、実戦力の養成と弱点の補強を中心とした学習を行います。春期から夏期にかけては基礎の総復習と応用問題への取り組み、秋期以降は過去問演習と直前対策に重点を置きます。
実際の古文について、こちらのサイトで ”両頭の蛇” について分かりやすく解説しています。
【全文&現代語訳つき】「両頭の蛇」って実はエモい!現代語訳・意味・テスト対策までまるわかり
季節ごとの重点項目
春期(4月〜6月)は基礎力の確認と弱点の発見に重点を置きます。これまでに学習した文法事項と語彙を総復習し、理解が不十分な箇所を特定します。春期講習や個別指導を活用して、基礎の穴を確実に埋めることが重要です。
夏期(7月〜8月)は集中的な読解演習の時期です。まとまった学習時間を確保できる夏休みを活用して、多くの古文作品に触れます。1日2〜3時間の古文学習時間を確保し、様々なジャンルの作品を読解します。
夏期では長文読解の練習も本格化します。共通テスト古文レベルの長さの文章に慣れることで、本番での時間配分感覚を養います。
秋期(9月〜11月)は実戦演習の中心時期です。共通テストの過去問や予想問題を使用して、本番形式での演習を重ねます。時間制限を厳守し、見直しの時間も含めた実戦的な練習を行います。
冬期(12月〜1月)は最終調整と弱点補強の時期です。過去問演習で発見された弱点を集中的に補強し、暗記事項の最終確認を行います。新しい問題に取り組むよりも、これまでに解いた問題の復習に重点を置きます。
日々の学習習慣作り
継続的な学習習慣の確立が古文の成績向上には不可欠です。毎日少しずつでも古文に触れることで、古文特有の文体に慣れ、読解スピードの向上が期待できます。
朝学習として古語の暗記を組み込むことをおすすめします。起床後の15分間を古語暗記の時間として確保し、前日に覚えた単語の復習と新しい単語の学習を行います。朝の時間は記憶力が高く、暗記学習に最適です。
音読練習は毎日の習慣として定着させることが重要です。夕食後や入浴後などの決まった時間に、10分程度の音読を行います。同じ文章を繰り返し読むことで、古文のリズムを体得できます。
週末の集中学習では、平日にできなかった読解演習や問題演習を行います。土曜日に新しい問題に取り組み、日曜日に復習と弱点補強を行うサイクルが効果的です。
学習記録をつけることも重要です。学習時間、取り組んだ内容、理解度を記録することで、学習の進捗状況を客観的に把握できます。また、どの分野が得意で、どの分野が苦手かを明確にすることで、効率的な学習計画の修正が可能になります。
塾・予備校・家庭教師の効果的な活用法
お子様の古文学習において、塾・予備校・家庭教師の活用は大きな効果をもたらします。それぞれの特徴を理解し、お子様の学習スタイルや目標に応じて最適な選択をすることが重要です。効果的な活用方法をご紹介します。
大手予備校の古文講座
大手予備校(河合塾、駿台、代々木ゼミナール等)の古文講座は、長年の指導実績に基づいた体系的なカリキュラムが特徴です。共通テスト古文対策に特化したコースでは、出題傾向の分析から実戦的な解法まで効率的に学習できます。
河合塾の「古文読解」講座では、文法事項の確認から始まり、段階的に読解力を向上させるカリキュラムが組まれています。特に記述式の現代語訳練習が充実しており、正確な文章理解力の向上が期待できます。
駿台の古文講座は、論理的なアプローチに定評があります。感覚的な読解ではなく、文法的な根拠に基づいた読解方法を指導するため、安定した得点力を身につけることができます。
代々木ゼミナールでは、講師の個性を活かした授業が特徴的です。有名講師による分かりやすい解説と、記憶に残りやすい指導方法で、多くの受験生に支持されています。
大手予備校の利点は、豊富な教材と模試です。オリジナルテキストや予想問題により、多角的な演習が可能で、他の受験生との比較による客観的な実力把握もできます。
個別指導塾の選び方
個別指導塾は、お子様一人ひとりの理解度やペースに合わせた指導が可能なため、古文が特に苦手なお子様や、特定の分野を集中的に強化したいお子様に適しています。
個別指導塾選びでは、古文指導の実績を重視することが重要です。古文は専門性の高い科目であるため、経験豊富な講師による指導が不可欠です。体験授業を通じて、講師の指導スタイルがお子様に合うかどうかを確認することをおすすめします。
明光義塾や個別教室のトライなどの大手個別指導塾では、共通テスト古文対策に特化したカリキュラムが用意されています。お子様の弱点を詳細に分析し、オーダーメイドの学習プランを作成してもらえます。
個別指導では、質問しやすい環境が大きなメリットです。集団授業では質問しにくい基本的な事項や、理解が曖昧な部分について、遠慮なく質問できる雰囲気作りが重要です。
進度の調整も個別指導の特徴です。理解が遅れている分野については時間をかけて丁寧に指導し、得意分野については発展的な内容まで学習することが可能です。
個別指導塾では、家庭学習の管理まで行ってくれる場合が多く、お子様の学習習慣確立にも効果的です。宿題の出し方や復習方法についても、個人に合わせた指導を受けることができます。
家庭教師の効果的な活用
家庭教師は最も個人に特化した指導形態であり、お子様の性格や学習スタイルに完全に合わせた指導が可能です。特に古文に対して苦手意識が強いお子様には、マンツーマンでの丁寧な指導が効果的です。
家庭教師選びでは、古文の専門性と指導経験を重視します。大学生のアルバイト講師よりも、プロの家庭教師や元予備校講師など、豊富な指導経験を持つ講師を選択することをおすすめします。
トライ、家庭教師のノーバス、学研の家庭教師などの大手派遣会社では、講師のプロフィールや指導実績を詳しく確認できます。共通テスト古文の指導実績がある講師を選択することが重要です。
家庭教師の最大の利点は、完全オーダーメイドの指導です。お子様の理解度に応じて、基礎からじっくりと積み上げることも、応用問題に集中することも可能です。また、学習時間の融通が利くため、部活動や他の習い事との両立もしやすくなります。
学習環境の最適化も家庭教師ならではの特徴です。自宅という慣れ親しんだ環境で学習することで、リラックスして集中できる場合が多く、特に人見知りのお子様には適しています。
家庭教師を選ぶ際は、相性を最も重視することが大切です。学力向上のためには、講師との信頼関係が不可欠であり、複数の講師と面談を行って最適な講師を選択することをおすすめします。
オンライン学習サービスの活用
近年、オンライン学習サービスも充実しており、従来の塾・予備校・家庭教師と組み合わせて活用することで、より効果的な学習が可能になります。
スタディサプリでは、有名予備校講師による古文講座を自宅で受講できます。共通テスト古文対策講座では、出題傾向の分析から解法テクニックまで体系的に学習できます。繰り返し視聴が可能なため、理解が不十分な箇所を何度でも復習できます。
進研ゼミやZ会などの通信教育では、個人の学習進度に応じた教材が提供されます。定期的な添削指導により、記述問題の答案作成能力も向上させることができます。
オンライン家庭教師サービスも充実しており、全国の優秀な講師による指導を受けることが可能です。地方にお住まいで、近くに適切な塾や予備校がない場合には特に有効な選択肢です。
オンライン学習の利点は、時間と場所の制約が少ないことです。部活動や他の習い事で忙しいお子様でも、空いた時間を有効活用して学習を進めることができます。
ただし、オンライン学習では自己管理能力が重要になります。計画的な学習を継続できるよう、保護者による適切なサポートが必要です。
まとめ:合格への道筋と継続的な学習の重要性
共通テスト古文で安定した高得点を獲得するためには、体系的で継続的な学習アプローチが不可欠です。お子様の現在の学力レベルと目標を明確にし、適切な学習方法と教材を選択することが成功への第一歩となります。
学習の優先順位と効率化
古文学習において最も重要なのは、基礎力の確実な習得です。文法事項と基本語彙を疎かにしたまま応用問題に取り組んでも、安定した成果は期待できません。まず動詞の活用、助動詞の意味・用法、敬語の基本を完璧にマスターすることから始めます。
次の段階では、読解力の段階的向上を図ります。短い文章の精読から始めて、徐々に長文読解に移行します。音読練習を継続的に行い、古文特有のリズムと表現に慣れることが重要です。
問題演習の充実も欠かせません。様々な形式の問題に取り組むことで、出題パターンに慣れ、効率的な解法を身につけることができます。特に共通テスト古文の特徴である長文読解問題については、時間配分を意識した練習が重要です。
学習の効率化には、弱点分析と重点的な補強が効果的です。模試や問題演習の結果を詳細に分析し、理解が不十分な分野を特定して集中的に学習することで、効率的な成績向上が期待できます。
長期的な視点での学習計画
共通テスト古文の対策は、短期間の詰め込み学習では限界があります。高校1年生から計画的に学習を積み重ねることで、確実な実力向上が可能になります。
1年生では基礎固めに重点を置き、2年生で応用力を養成し、3年生で実戦力を完成させるという3年間の学習ロードマップを描くことが重要です。各段階で適切な目標を設定し、達成度を定期的に確認することで、着実な進歩を実感できます。
継続的な学習習慣の確立も重要です。毎日少しずつでも古文に触れることで、古文への親しみやすさが増し、読解スピードも自然に向上します。特に音読練習は、短時間でも継続することで大きな効果を発揮します。
季節講習や集中学習期間を有効活用することも大切です。夏休みや冬休みなどのまとまった時間を利用して、弱点分野の集中補強や大量の問題演習を行うことで、学習効果を最大化できます。
保護者としてのサポート方法
お子様の古文学習において、保護者の適切なサポートは学習効果を大きく左上させます。まず、学習環境の整備が重要です。静かで集中できる学習スペースの確保と、必要な教材や辞書の準備を行います。
学習進度の管理についても、保護者の役割は重要です。定期的に学習状況を確認し、計画通りに進んでいるかをチェックします。ただし、過度な干渉は避け、お子様の自主性を尊重することが大切です。
塾・予備校・家庭教師の選択においては、保護者の判断が重要になります。お子様の性格や学習スタイルを考慮して、最適な学習環境を提供することが成績向上につながります。
精神的なサポートも忘れてはいけません。古文は多くの受験生が苦手とする科目であり、成果が見えにくい場合もあります。長期的な視点で励まし、小さな進歩も認めて褒めることで、お子様の学習意欲を維持することができます。
模試の結果についても、点数だけでなく、具体的な改善点を一緒に分析することが重要です。どの分野が伸びているか、どこに課題があるかを客観的に把握し、今後の学習方針を調整します。
最終的に、共通テスト古文で高得点を獲得するためには、基礎力の確実な習得、継続的な読解練習、そして適切な指導者からのサポートが不可欠です。お子様に最適な学習方法を見つけ、長期的な視点で取り組むことで、必ず成果につながります。古文は一朝一夕では身につかない科目ですが、正しい方法で継続的に学習すれば、確実に実力向上が期待できる科目でもあります。